1年の折り返し『夏越しの祓』
- 2017年6月28日
- 読了時間: 3分
茅の輪とは、茅(ちがや)という草で編んだ輪のことです。 日々生活していると、さまざまな罪や穢れが生じると考えられてきました。そこで、茅の輪や形代(かたしろ)などで罪や穢れを祓う大祓(おおはらえ)を行うようになりました。
昔、一人の旅人が現れ、ある兄弟に一夜の宿を乞いました。弟は裕福であるにもかかわらず旅人を冷たく断りましたが、兄の蘇民将来(そみんしょうらい)は貧しいながらも手厚く旅人をもてなしました。実はこの旅人は武塔神(むとうしん。スサノオノミコトと同一視されている)で、蘇民将来へ災厄を祓う茅の輪を授けました。蘇民将来は、武塔神の教えに従い茅の輪を腰に付けたところ、疫病から逃れられ、子々孫々まで繁栄したということです。 この話に基づき、茅の輪くぐりをしたり、家の玄関に蘇民将来のおふだをつけたりするようになりました。











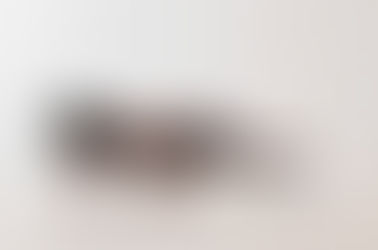






















コメント